よく音感がいい とか 音感がある
などと言いますが、そもそも〝音感〟ってなんでしょう?
絶対音感、相対音感というのはありますが、私はそれだけではないと感じています
音の高低、長短、強弱、調性、音質や音色の聴き分け、音に対する美意識‥
字の如く〝音を感じる〟能力のことではないかと思います
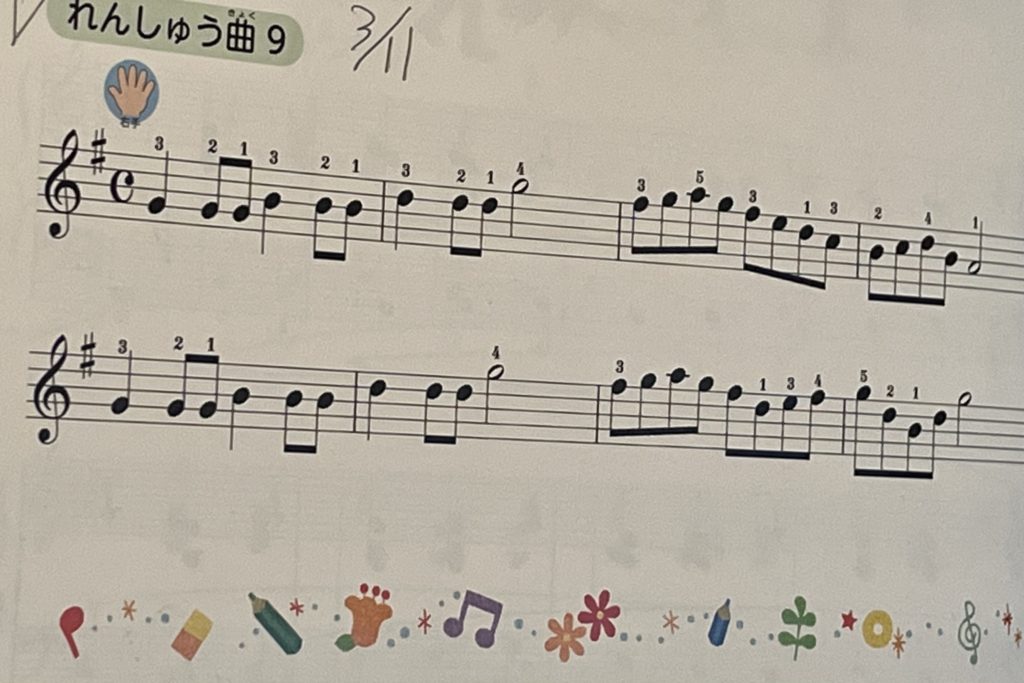
今日、ある生徒さんが弾いてきたト長調のこちら↑
初めて私がレッスンでみる曲でしたが、ファ♯の調号をつけないまま弾いてきた😓
これって、調号見るの忘れた‥とかそういう問題じゃなくて…
Q. なんか変だと思わない?
A. 思わない
‥😕ありゃ、こりゃ困った⤵︎
仕方なく、ファ♯つけてないのとついたのと2種を何度か弾いてあげた
ねぇ、どっちかが「まぬけト長調に聴こえなかった?」と聞いてみましたら
「ほんとだ!ファ♯つけないで弾くと、まぬけな曲に聴こえた😅」と、ようやく気付いてくれました
要は、音感ってよく聴いてないと育たないものなんじゃないでしょうか‥
注意深く聴けば、ある程度は誰でも育つのではないでしょうか‥
興味をもって聴いているかいないか‥これがとても大きいと思います!
ちゃんと聴けばわかるのに、ただ鳴らしているだけで、音楽として捉えようという意識をもたない限り、いい音には繋がらない‥のではないかと思いました
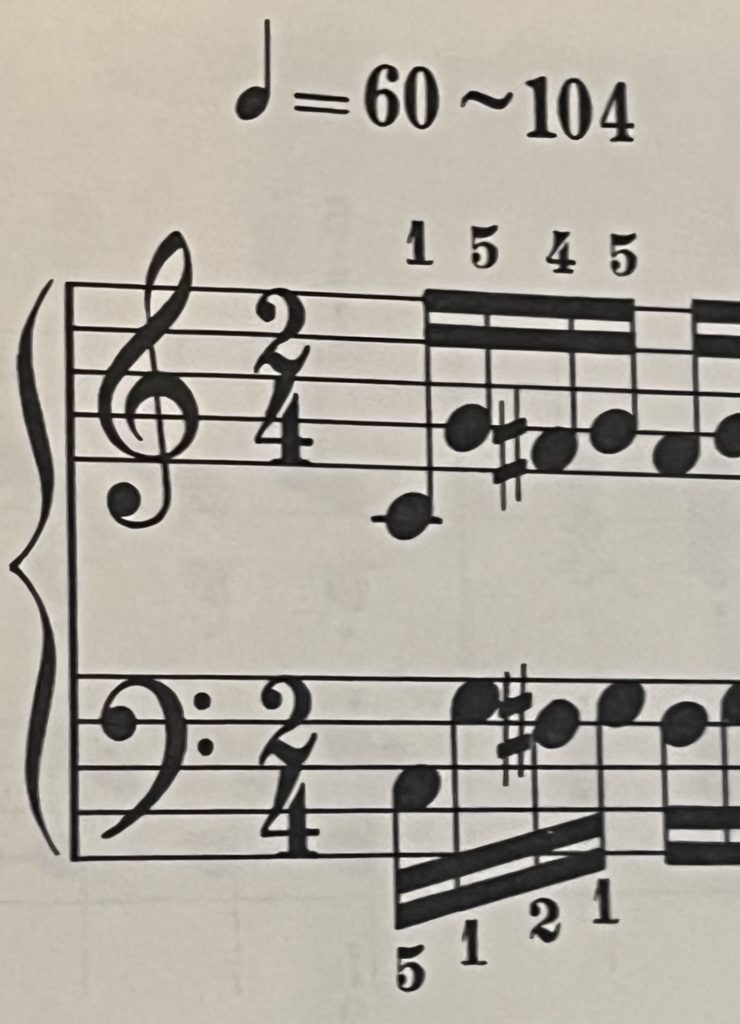
別の曲に移って、速度記号が書いてありましたので、この範囲内で弾くことが目標ね!と言いました
途中速くなっちゃったり、遅くなってしまったりしたので、メトロノームで合わせました
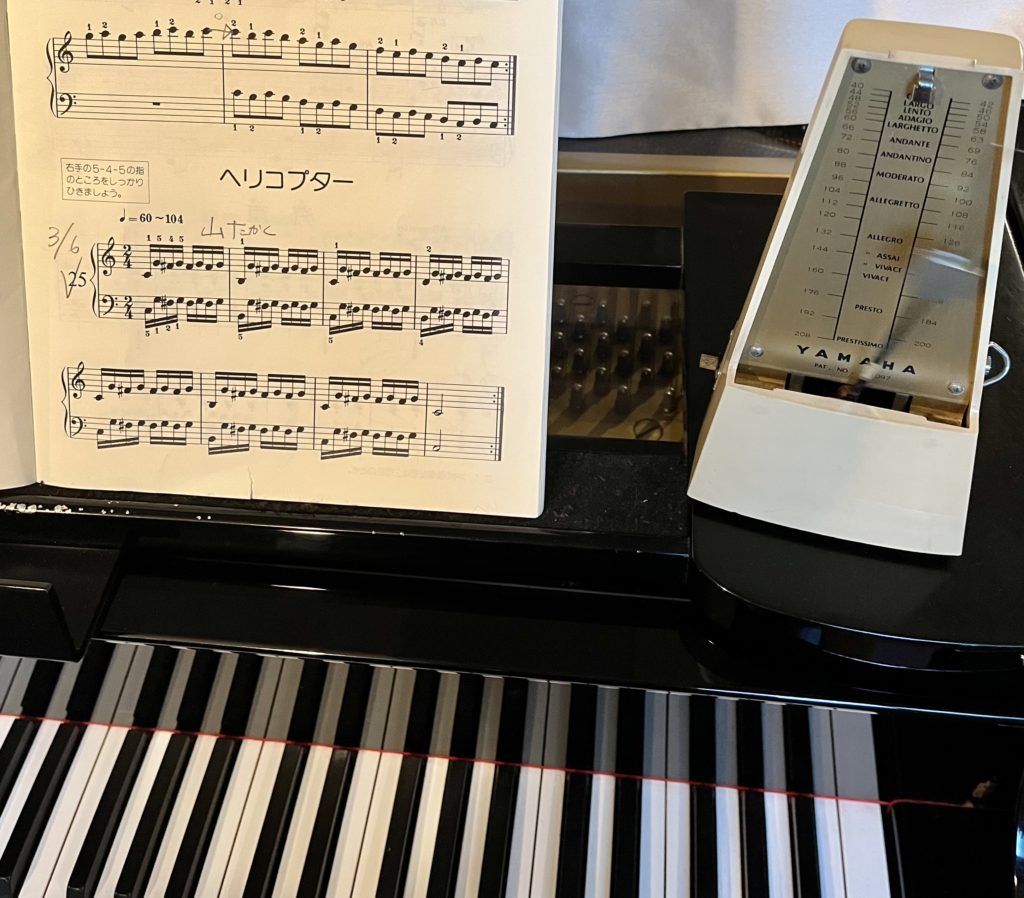
速度も立派な〝音感〟の1つだと感じます
同じ速さでないと、そもそもリズムにのれませんよね?
へんてこな音楽になってしまいます😓
今日は、まぬけ や へんてこ という言葉を敢えて使いました
普通に調号ついてないわよ、とか、速さが一曲の中で変わってしまって変よ、というあたりき車力の言葉を言っても、生徒さんには注意された💦という気持ちにしかなってもらえないように感じ
できるだけ明るく、何なら笑いながら、間違いを聞いてもらえるように、と‥😊
2/4拍子とあり、拍子感覚も音楽の大事な要素です
〜いい音が好き、綺麗な音がいい〜
と思ってもらえる〝耳〟を育てること
音感と一言で言っても色々な要素があり
いい音に対する〝感覚〟と〝勘〟を総じて〝音感〟
なので、音感の良さと勘の良さ は、比例するように思います
勿論、音楽の勘ですが‥
なんやカンや、カンカン言いまして、失礼致しました笑

